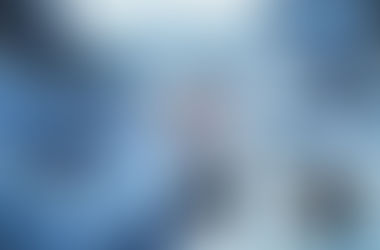文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設エネルギー性能の効果は光熱費の削減だけでない(4)
第四の効果は、地域の建築事業者の技術力向上です。建物の躯体性能を向上させることは、作業工程が増え、施工に注意が必要となるため、建築事業者の手間賃を増加させることになります。とりわけ、中小規模建物や住宅、既存建物の躯体性能の向上は、大資本のゼネコンからすれば、営業コストばかり...


文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設エネルギー性能の効果は光熱費の削減だけでない(3)
第三の効果は、設備更新費用の縮小です。建物の長寿命化と似ていますが、異なる概念です。例えば、10億円の建設費を要し、10年ごとに1億円、20年ごとにさらに1億円の設備更新費を要する公共施設Aと、12億円の建設費を要し、10年ごとに5千万円、20年ごとにさらに5千万円の設備更...
文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設エネルギー性能の効果は光熱費の削減だけでない(2)
第二の効果は、建物の長寿命化です。公共施設を長期にわたって使用できれば、その分だけ税金の投入を減らせます。例えば、10億円の建設費を要し、10年ごとに1億円の維持管理費も要する公共施設を仮定しましょう。30年ごとに建て替える場合、60年間のトータルコストは、24億円です。一...


文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設エネルギー性能の効果は光熱費の削減だけでない(1)
公共施設のエネルギー性能を高める効果は、光熱費の削減だけにとどまらず、多岐にわたります。日本では、暑さ寒さに耐えて光熱費をケチる傾向があり、光熱費の使用実績から削減見込額を出すと、エネルギー性能の高い建物はペイしないと評価されることもあります。すると、エネルギー性能の低い建...


文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 エネルギー性能の高い公共施設をつくる(6)
公共施設は、地域熱供給の核にもなります。熱供給とは、個々の建物や部屋で冷暖房や給湯の熱源設備(空調や給湯器など)を取り付けて需要を賄うのでなく、センターに熱源設備(ボイラーなど)から冷暖房や給湯の「熱」を配るシステムです。それを敷地の異なる複数の建物間に配ると、地域熱供給と...


文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 エネルギー性能の高い公共施設をつくる(5)
設計プロセスを指定することに加え、エネルギー関係の設計・設備の検討に際しての優先順位を基本設計の仕様書に指定しておけば、より効果的です。これは「予算度外視で究極の高いエネルギー性能の建物をいったん設計」する段階での優先順位です。予算額に達するまで引き算するときの根拠は、費用...
文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 エネルギー性能の高い公共施設をつくる(4)
ZEB/ZEB Nearly概念を超えて、真に持続的なエネルギー性能の高い公共施設を設計するためには、設計プロセスを基本設計の仕様書で指定することが必要になります。「この手順で設計し、その手順を踏んだことを客観的に示せるようにしてください」と、自治体が仕様書で指定すれば、設...


文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 エネルギー性能の高い公共施設をつくる(3)
政府のZEB/ZEB Nearlyだけでは、真に持続的なエネルギー性能の高い公共施設に不十分なため、自治体職員の積極的な取組みが必要になります。公共施設の仕様は、どうしても技術職員に任せがちとなりますが、事務職員であっても大いに意見を述べることが大切です。そのためには、事務...


文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 エネルギー性能の高い公共施設をつくる(2)
政府は、2020年までに新築公共施設でZEBを実現し、2030年までに新築建物の平均をZEBにすると目標を立てています。これは、2014年に策定されたエネルギー基本計画に記載されています。一見すると、意欲的な目標に思えます。けれどもEUでは、2019年に新築公共施設で義務化...
文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 エネルギー性能の高い公共施設をつくる(1)
前回までの講座で、公共施設を持続可能にするために考慮すべき事項が、6点あることを解説しました。第一は目的、第二は立地、第三は稼働、第四は寿命、第五は費用、第六はパリ協定です。持続可能といっても、環境面だけに配慮すればいいわけでなく、環境以外の視点も持続性を決定づけるのです。...