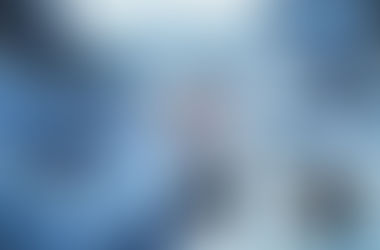文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設から始める(8)
第六の事項は、パリ協定です。パリ協定とは2020年以降の地球温暖化対策に関わる国際ルールで、2016年11月に発効しました。「世界の平均気温上昇を工業化以前から2度以内に抑える」ために「今世紀後半の温室効果ガス排出を実質ゼロにする」ことを目指し、各国に対策を義務付けています...
文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設から始める(7)
第五の事項は、公共施設の費用です。地方財政法第4条で「目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」と定められているとおり、公共施設の費用についても「最小の限度」であることが求められています。...
文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設から始める(6)
第四の事項は、公共施設の寿命です。施設を何年使うかによって、費用対効果や財政への負担は大きく変わってきます。鉄筋コンクリート造でも鉄骨造でも木造でも、手抜きせずに建て、適切にメンテナンスすれば、100年を超えて使用できます。...
文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設から始める(5)
第三の事項は、公共施設の稼働です。多くの人によって使われたり、多くの売上をあげたり、多くの課題解決につながっていれば、その公共施設は稼働率の高い状態にあります。もちろん、単に使われていればいいのではなく、目的にどれだけ寄与しているのかが、根本的には問われます。...
文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設から始める(4)
第二の事項は、公共施設の立地です。目的からして、公共施設の建設(建替え・改修も含みます)以外に選択肢がないとなれば、次は、どこに設けるかを検討します。公共施設は、いったん建設すれば、長期にわたって移動できません。現在だけでなく、長期的な視点を含めて多面的に立地を検討する必要...
文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設から始める(3)
公共施設を持続可能にするため、考慮すべき事項は、大きく6点あります。第一は目的、第二は立地、第三は稼働、第四は寿命、第五は費用、第六はパリ協定です。持続可能といっても、環境面だけに配慮すればいいわけではありません。それどころか、環境以外の視点が持続性を決定づけるといっても過...


文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設から始める(2)
持続可能な地域づくりにおいて、どこの自治体でも第一歩としてもっとも取り組みやすい案件は、公共施設を持続可能にすることです。公共施設と一口にいっても、その種類は様々です。行政の庁舎はもちろんのこと、学校や図書館、保育園、病院、市民ホール、競技場、ごみ処理場、浄水場、公営住宅な...
文系自治体職員でもできる!持続可能な地域のつくり方講座 公共施設から始める(1)
持続可能な地域をつくることの重要性は、多くの自治体職員に理解されているでしょう。ただ、日常業務に追われてそのことをアタマの片隅にしまっていたり、理不尽な指示に慣らされて正反対のことをしていても気づかぬふりをしていたり、何となく理解していても具体的に何をすべきか分からなかった...