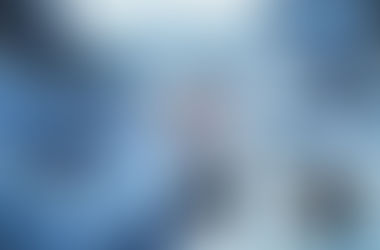人口減少でも医療費・介護費は増加し続ける
人口減少といっても、すべての年代が均等に減少するわけではありません。図表のとおり、日本の人口ピークは2008年でしたが、65歳以上の人口ピークは2040年と推計されています。2016年の65歳以上の人口は3,459万人で、2040年には3,920万人まで増加すると見込まれて...


ここが凄い!ニッポンのまちづくり
日本の都市でしばしば見かける、特徴的なまちづくりを紹介します。全国の自治体が国と歩調を合わせ、長年にわたって徐々につくり込んできました。日本の自治体には、都市政策がないと批判されることもありますが、そのようなことは決してありません。これらのまちづくりは、自治体の都市政策の集...


貧困対策での住宅の重要性を16世紀に見抜いていたフッガー
人口減少社会では、貧困世帯の所得を高め、地域経済の需要を確保することが重要になります。貧困世帯の所得を高めるためには、家賃・光熱費・交通費からなる「実質的な家賃」を減らし、自らや子どものための資金を捻出することが考えられます。ところが、光熱費・交通費のエネルギー費用は、貧困...


貧困世帯から資産世帯、そしてサブリース企業への所得移転
貧困世帯が民間の賃貸住宅に住むということは、貧困世帯から資産世帯への所得移転を意味します。ここでは、資産世帯について、自らの居住に用いない土地や家屋を所有する世帯のことを指します。賃貸住宅の居住者は、大家である資産世帯に対して毎月の家賃を支払いますが、それを資産世帯から見れ...


貧困世帯を直撃しやすいエネルギー費用
貧困世帯は、エネルギー費用の負担割合が高くなりやすい構造のなかに置かれています。ここでのエネルギー費用とは、具体的に冷暖房費とガソリン代です。これらが、中所得・高所得の世帯よりも、家計を圧迫しやすいのです。 多くの貧困世帯が居住する民間賃貸住宅の主流は、軽量鉄骨造です。いわ...


貧困脱出の足かせとなっている「実質的な家賃」
貧困からの脱出を目指すとき、最初に行うのは支出を見直すことでしょう。不要不急の支出を削減し、生きるために不可欠な支出や、貧困脱出に必要な支出に回すのです。金銭的な余裕ができれば、時間的な余裕もねん出しやすくなりますので、就職活動や資格の勉強、生活の改善なども行いやすくなりま...


ひとり親・子どもの貧困対策は人口減少の影響緩和に多面的な効果
人口減少の影響を緩和する観点で、貧困対策のなかでも、より多面的な効果を期待できるのが、子どもの貧困対策です。子どもの貧困対策とは、親の所得と、子どもの生育環境や教育環境の関係を切り離す政策です。親が金持ちでも貧乏でもどのような状態でも、すべての子どもに対して、充分な知識や体...


人口減少で重要性を増す貧困対策
急激な人口減少が避けられないなかで、生活や経済への悪影響を緩和するために、貧困対策がさらに重要となります。一見すると、人口減少と貧困対策がどのように結び付くのか、分かりにくいかも知れません。実際、国の地方創生総合戦略は、貧困対策を人口減少対策に位置付けていません。多くの自治...


人手不足を逆手に取る地域づくり
人手不足は、地域の生産力と所得を減少させるため、自治体と地域経済界が直視すべき、重大な課題です。自治体は、不要不急の官需を抑制し、民需から人手を奪うことを最小限にしなければなりません。公的な人材育成の仕組みを早急に整え、転職のハードルを下げる必要もあります。経済界は、経営者...


構造的な差別が地域経済を衰退させる
人手不足は、働くことや社会参加を望む人々を阻害することによっても、助長されています。働くことを望む多くの人々が、地域に潜在しています。ハードルが取り除かれれば、そうした人々が働き始め、人手不足を緩和できます。 阻害されている人々の典型は、子どものいる女性です。主要国における...