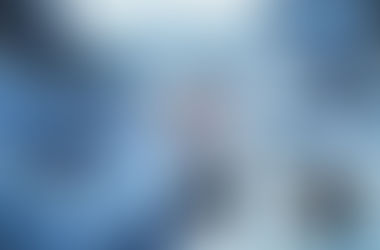老朽化による建替え・改修の公共施設には、パリ協定対応が必須
公共施設も重要なインフラですが、全般的に老朽化が進んでいます。【図表】は、市区町村が保有する公共施設の延床面積の推移で、2020年には約3分の1が築50年、約半分が築40年以上の施設ということになります。 そのため、全国の自治体で現在、多くの公共施設の新築、建替え、改修が進...


インフラの取捨選択には熟議と合意形成が不可欠
インフラの取捨選択は、地域社会を存続させる上で、避けて通れない道です。人口減少に合わせて、維持すべきインフラを減量しなければ、インフラが使えなくなるか、インフラコストに潰れてしまうかのどちらかです。いずれにしても、住民生活と地域経済を圧迫します。...


インフラ整備の経緯と現状を踏まえた取捨選択
人口減少においても、住民生活と地域経済の基盤となるインフラを安価なコストで維持するためには、時間をかけて取捨選択する必要があります。稼働率・効果の低いインフラを廃止し、稼働率・効果の高いインフラに投資を集中していくのです。...


人口は虫食い状態で減少し、インフラ網を蝕む
人口減少は、地図上で見ると、虫食い状態で進行します。過疎地域や人口密度の薄い都市周縁部から徐々に、秩序だって減るのではありません。ランダムに居住者がいなくなり、オフィスがなくなり、工場・商業施設が撤退していくのです。 その理由は様々であるため、自治体が何もせずに整然と進行す...


人口減少でインフラ維持が困難になる
2000年代まで(もしかしたら今でも)、人口増加を前提としたインフラ整備を続けてきたため、維持すべきインフラが膨大な量になっています。既に人口減少となっていますので、一人当たり維持すべきインフラが毎年、増加し続けています。...


人口増加に合わせてインフラを拡大してきた日本
戦後の日本は、【図表】のとおり、人口増加に合わせてインフラ整備を拡大してきました。それは、1950年に制定された国土総合開発法に基づき、具体的なプロジェクトは全国総合開発計画(全総)に則って整備されました。1962年の第一次全総から、1998年の「21世紀の国土のグランドデ...


エネルギー分野で新たな価値を創造する
地域経済における再エネの利点は、固定価格買取制度で環境・社会面での価値が既に評価されていて、必ず売れることです。価格は、長期の投資回収と収益性を評価して設定されているため、慎重に事業計画を立てて順調に発電すれば、必ずペイできます。新たな価値が評価され、販売と事業性が保証され...


住宅の断熱投資を増やして医療費を削減する
負の効用に由来する経済活動を正の効用に由来するものに転換することでは、断熱住宅の普及による循環器系疾患の抑制が有効です。ブログ「医療費・介護費を減らすと同時に地域経済を活性化」で解説したように、新築・改修で住宅の断熱性・気密性を高めれば、循環器系疾患に代表される季節変動のあ...


再エネと省エネは輸入置換の優等生
輸入置換とは、域外から購入している製品・サービスを域内供給に切り替えることです。それにより、域外の供給者が手にしている対価を、域内の供給者が手にするようになります。その分だけ域内の所得が増加し、さらなる投資・消費の拡大につながります。それを繰り返すことで、域内の産業が発展し...