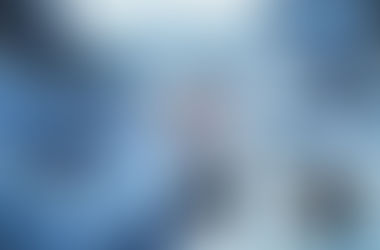地域経済5政策を進めるカギはエネルギーにある
それでは、具体的にどのような地域経済政策を展開すればいいのでしょうか。労働生産性の向上、成長産業への働き手の移動、輸入置換、正の効用をもたらす経済活動、価値の創出という5つの政策方針があっても、手法がなければ絵に描いた餅です。行政資源に乏しい自治体とすれば、一つで複数の効果...


地域経済で必要な5つの政策
人口減少、需要過少、技術転換という3つの課題に対し、5つの政策を打つことで対応できます。すべてが自治体で完結できる政策ではなく、国レベルで取り組むべきものもあります。ただ、そうした政策についても、自治体から積極的に提案・要望することで、実現を目指していくことが重要になります...


地域経済を取り巻く3つの課題
第一の課題である人口減少は、地域経済を縮小させる方向で、強い圧力をかけてきます。もっとも大きい影響は、人口減少に伴う域内需要の縮小です。一人当たりの年間消費・投資額が同じであれば、人口の減少に比例して経済が縮小します。また、ブログ「民需と官需で人手の奪い合い」で示したように...


医療費・介護費を減らすと同時に地域経済を活性化
冬に多い死因の冬と夏の落差について、寒冷地の方が大きいと限りません。図表は、北海道と栃木県の主要死因について季節変動を比較したものです。北海道の方が、栃木県よりも寒冷地であるにもかかわらず、季節変動がなだらかです。 これは、それらの死因について、外気温よりも室温が大きく影響...


冬に多く、夏に少ない死因
循環器系疾患の死亡率は、冬に増加し、夏に減少します。これは、寒い時期の急激な温度変化により、血圧の乱高下が発生し、血管の拡張・収縮の動きが追いつかないために、血管詰まりを起こすことが一因です。例えば、暖かい部屋にいる人が、薄着のまま寒い場所に出たり、寒い場所に薄着でいた人が...


たばこ税の健康保険財源化
循環器系疾患は、典型的な生活習慣病で、人々の生活状況を改善することで予防できます。効果的な予防方法で確立されているのは、禁煙(たばこを吸わないこと)、減塩(塩分を取り過ぎないこと)、運動です。国立循環器病研究センターによると、睡眠の質の改善やストレスの緩和など、様々な生活習...


医療費・介護費を圧迫する循環器系疾患
自治体経営の観点から医療・介護を見ると、サービス利用者数が将来にわたって一定で推移することが望ましい状態になります。利用者が増加する見込みであれば、施設を建設し、医師などの従事者を確保しなければなりません。利用者が減少する見込みであれば、既存施設の稼働率が低下し、施設経営を...


地方から都市に流入する高齢者
全国的に見れば、高齢者数は増加し続けますが、一部の地方は既に減少・横ばい状態になっています。例えば、長野県天龍村(約1,600人)は、1980年以降総人口が減少し続け、65歳以上の人口も2005年をピークに減少へ転じています。同様に、既に高齢者数すら減少に転じている市町村は...